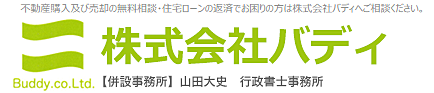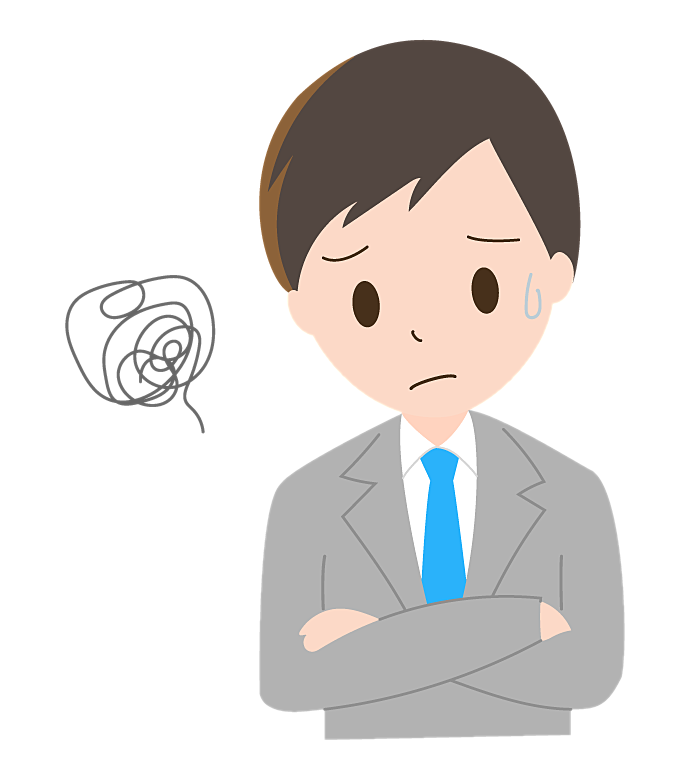再建築不可物件の購入はあり?なし?
こんにちわ(^^)/ 今回は「再建築不可物件」についてお話したいと思います。スーモやアットホームなどのポータルサイトで物件を探していて、「おっ、安いなぁ‼」と思ってクリックしてよく見たら、「再建築不可です。」と書かれていた経験はないですか?意外と多いと思います。
「再建築不可物件」とは、建て替えのできない物件のことです。そのままです(^_^;) 現在の建築基準法の規定ができる前から建っている物件はそのままでいいんですが、一度取り壊してしまうと、新たに建築ができません。
そんな物件あるの?って思う方も多いかもしれませんが、意外と多いですよ。「再建築不可物件」で一番多いケースは「接道義務」を満たしていない土地です。建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけません。理由は、火災や地震などの災害が起きた時の避難経路と、消防車や救急車が通れる経路を確保するためです。
家を建てる時は建築基準法により様々な制約があり好きな場所に自由に建てられないこともありますが、「接道義務」をクリアして可能になるケースがあります。
まずは、セットバック(後退)して道路幅員4mを確保するケースです。セットバック(後退)とは、建築基準法では前面道路幅が4m以上ない場合、建て替えるときは4mの幅を確保する必要があるので、その分下がったところしか家を建てられません。道路の向かい側が宅地の場合は、道路の中心線からそれぞれが2mセットバック(後退)しなければなりません。道路に提供しなければいけない部分が出てくるので、利用できる敷地は狭くなりますが、セットバック(後退)によって建て替えが可能になります。
次に、隣地の方に土地を譲っていただき、2mを確保するケースです。先程お伝えしたように、建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接していなければ家は建てられないというルールがあります。なので、1mしかない場合、隣地の方が利用していなかったり空地になってたりして、ご相談して譲っていただくことができれば、2m確保できることになるので、建て替えは可能になります。実際は、隣地の方が承諾してくれるかどうかは分かりませんし、隣地の方が承諾してくれたとしても、購入費用はもちろんですが、測量費用、登記費用などを負担しなければいけません。なかなかハードルは高いですね。
それでは、次に再建築不可物件のメリットをお伝えしたいと思います。
まずは、価格です。再建築ができないので、需要が少なく、相場よりかなり格安で売りに出ています。
次にリノベーションやリフォームはできるという点です。建替え工事はできませんが、骨組みや柱などを残したままリノベーションやリフォームをして自分好みの住空間を作ることができます。安く購入できるので、その分をリフォーム費用にまわすことができますね。弊社も、再建築不可物件を買取りさせていただいたことも多々あります。購入後は、リフォームして、貸家として提供しています。貸家はアパートやマンションと比べると数が少なく、又、戸建てに住みたいというお客様は多く人気なので、募集開始後、早めに入居者が決まっているケースが多いです。不動産投資としては、格安で始めることができるのでお薦めですよ。
ただ、もちろん、デメリットもあります。
まずは、①リフォーム費用が高額になる可能性があります。
「接道義務」を満たしていない土地は進入経路が狭く、重機や作業車が入れないのでどうしても工事費が高くなります。
次に、②災害で家屋が全壊、焼失すると、建て替えできません。
もしリフォームした家が、火災や地震などの災害で全壊、焼失した場合、家を建て直すことができないので土地だけ残ってしまいます。家を建てられない土地の価格は下がってしまい、売却するにしても需要がないため、なかなか買い手が見つからないということになってしまいます。
そして、③住宅ローンが利用できません。
再建築不可物件は、基本的に、住宅ローンが利用できません。金融機関は、再建築不可物件は担保価値がないとみなすので融資してくれません。なので、物件は現金で購入して、リフォーム費用については、リフォームローンを組む必要があります。リフォームローンは担保として取らないケースが多いのでリフォームローンは組むことができます。ただ、住宅ローンと比較して、金利がとても高く、返済期間も短いです。
このように、再建築不可物件はメリット、デメリットがありますが、デメリットのもたらす要因のほうが大きいように思われます。そして、購入後もハードルが高いですね。なので、まとめとしては、購入の際は「接道義務」を解消できる可能性があるのかないのか、将来的な使い道、予算の組み方などを事前にしっかり検討してから進めることが大事だと思います、ご参考いただければと思います。

関連した記事を読む
- 2025/05/20
- 2025/05/16
- 2025/05/14
- 2025/05/13