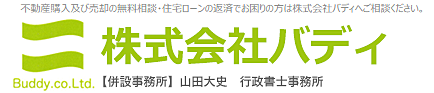任意売却 配分案の内容
こんにちわ、今回も任意売却シリーズですが、「配分案の内容」についてお話したいと思います。任意売却で購入希望者が決まると、売却代金をどのように配分するのか配分調整が必要になります。これがとても重要です。売却代金の中からサービサー(債権者)合意のもとで、売却に必要な費用も配分していただき控除されます。つまり、控除していただける範囲であれば、債務者は費用を用意する必要がありません。これが任意売却の最大のメリットといっても過言ではないと思います。それでは、詳しくみていきましょう。
まずは、「仲介手数料」です。任意売却が成立したときに不動産会社にお支払いする費用です。例えば、1,000万円で成約になったときは、{(1,000万円×3%)+6万円}×1.1(消費税)=396,000円です。
ですから396,000円は売却代金から控除されます。ご自身で用意する必要はありません。
次に、「抵当権抹消登記費用」です。住宅ローンを組んでいるということは抵当権が設定されているので、任意売却が成立できたら、この抵当権を抹消する必要があります。その際、司法書士にお支払いする費用が「抵当権抹消登記費用」です。この費用も売却代金から控除されます。
次は、マンションの場合ですが、管理費等の滞納分です。住宅ローンを滞納している場合、マンションの管理費等も滞納しているケースが多いです。その滞納している管理費等についても売却代金の中から配分していただけます。しかし、上限があります。長期に渡って滞納している場合、上限を超えると不足分が発生します。そして、駐車場代や遅延損害金などは認められないケースが多いですので、事前にサービサー(債権者)に確認しておきましょう。
次は、滞納している税金分です。これらも売却代金の中から配分していただけます。しかし、サービサー(債権者)に認めてもらえるのは「差押登記」が入っている場合のみのケースが多いので気を付けてください。又、売却代金から配分してもらえるのは「固定資産税都市計画税」の部分のみです。もちろん、上限があります。遅延損害金、国民健康保険料、軽自動車税、市県民税などは配分してもらえません、ご注意ください。
そして、「抵当権抹消承諾費用」です。業界では、「ハンコ代」と言われます。現在はあまりありませんが、ひと昔前は1番抵当権者が住宅金融金庫、2番抵当権者が民間金融機関になっているケースがよくありました。任意売却はこの2番抵当権者、3番抵当権者にもハンコ代(抵当権抹消承諾費用)を売却代金から配分して、抵当権抹消に協力してもらう必要があります。ハンコ代についてはおおよその目安は決まっていますが、その金額で協力してくれるかどうかは2番、3番抵当権者次第です。目安の範囲内で調整できれば問題ありませんが、多額をもとめてきた場合は、調整がつかず、任意売却が成功しません。ただ、任意売却が成功しなくて競売になった場合、2番、3番抵当権者は1円も回収できないことが多いため、彼らも歩み寄ってくる可能性は高いです。ここの調整が成功できるかどうかの大きな鍵になりますね。
最後に「引越し代」です。任意売却を行なうメリットとして「引越し代の捻出ができる」が挙げられます。以前はほとんどのサービサー(債権者)が売却代金の一部から引越し代として約10~30万円程配分してくれていました。そして、その引越し代で住替え先に移ることができました。しかし、近年では、ほとんどのサービサー(債権者)が認めてくれません。ただ、自己破産をしている場合に限り10~20万円程度認めてくれる場合もあるので、事前に確認が必要です。
決済前までに引越しをしなければいけないので、事前にある程度の金額を貯めておきましょう。それでも捻出が難しいときは、買主様に事情を話して、売買代金とは別に売主様の引越し代を出していただけたこともあります。購入される方が不動産買取業者であれば理解してもらえますが、一般のお客様が購入される場合、「売主様の引越し代をなぜ私達が出さないといけないの?」という想いからなかなかご理解いただけないことが多いです。買主様からみれば当然だと思います。ご理解いたけたとしても少額だと思います。中には、購入自体を止める方もいらっしゃると思います。よって、この「引越し代」はできればご自身である程度貯めるようにしておきましょう。
このように、任意売却の売却代金の配分調整は、全ての関係者と話をして、配分調整した金額でご理解していただけるようにお願いをしてまとめていきます。全員の合意が必要になります。一人でも協力してもらえなかったら任意売却はまとまりません。なので、任意売却を取り扱う不動産会社は、任意売却できる期間内にまとめるために精一杯尽力します。この「配分調整」が最大のポイントです。

関連した記事を読む
- 2025/05/31
- 2025/05/30
- 2025/05/29
- 2025/05/24